<P.B.O.カクテルフェスティバル2010>
第1部 カクテルコンペティション
第2部 フェスティバルパーティー
PBOカクテルフェスティバル2010の開催が決定いたしました。会場は東京・飯田橋のホテル メトロポリタン エドモントです。第1部は若手バーテンダーの登竜門的存在のカクテルコンペティションを開催し、第2部のフェスティバルパーティーでは料理を楽しみながらスタンダードカクテルの提供や、サポートメンバー各社の取扱商品の試飲ブース、フレアバーテンディングやベリーダンス・ショーなどを予定しております。メンバーのみならず、カクテルにご興味のある愛好家の皆様の来場をお待ちいたしております。カクテルコンペティションエントリー資格はPBOメンバーのみとなっております。詳細は決定次第随時更新いたします。ご期待下さい。
日 時 2010年3月7日(日曜日) 13時30分〜19時
主 催 NPO法人プロフェッショナル・バーテンダーズ機構(P.B.O.)
協 力 社団法人泡盛マイスター協会
NPO法人カクテルコミュニケーションソサエティー
スコッチ文化研究所
全日本フレア・バーテンダーズ協会
P.B.O.サポートメンバー各社
会 場 ホテル メトロポリタン エドモント
東京都千代田区飯田橋3-10-8
コンペティションエントリー資格 P.B.O.メンバーのみ
チケット ビジター当日券 ¥12,000-(第1部・第2部共通)
ビジター前売り/ご予約券 ¥9,000-(第1部・第2部共通)
P.B.O.メンバー ¥8,000-(第1部・第2部共通)
コンペティション観戦のみ ¥2,000-(予約不要・当日精算)
問い合わせ
PBOカクテルフェスティバル実行委員会(洋酒博物館内 03-3571-8600 北村)
P.B.O.カクテルフェスティバル2010では、お酒の提供がございます。
未成年の飲酒及びお車での来場は固くご遠慮申し上げます。
※開催情報は今後も随時更新いたします。
※PDFデータを閲覧するためには、アドビリーダーが必要です。
アドビリーダーが必要な方は、アイコンをクリックしてダウンロードしてください。
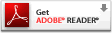
NPO法人プロフェッショナル・バーテンダーズ機構(PBO)







